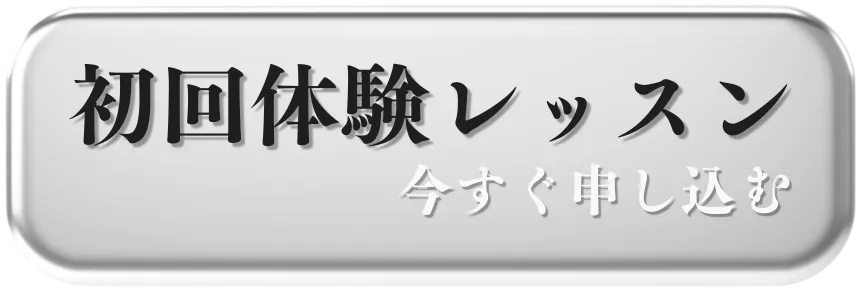ピラティスで根本から不調を解消!身体の左右差を改善するためには?

- 💎身体の左右差とは?なぜ起こる・見逃されるのか
- 💎なぜピラティスが左右差改善に選ばれているのか
- 💎自分の身体の左右差に気づくためのセルフチェック&基本エクササイズ
- 💎左右差を改善すると、こんな変化が生まれる
- 💎解剖学的な観点で見る、ピラティスが身体の左右差や不調改善に有効な理由
「鏡を見ると、片方の肩が下がっている気がする」「脚を組むと同じ方ばかり」「なんとなく身体が左右で違う感じがする」。
こうした“左右差”を感じたことがある方は多いのではないでしょうか。
左右差は決して特別なことではなく、ほとんどの人の身体に存在しています。
ただし、その差が大きくなると、姿勢の崩れや肩こり・腰痛などの慢性的な不調に繋がることがあります。
そして、この「左右のアンバランス」を整えるうえで、ピラティスは非常に有効なアプローチです。
ピラティスは単なる筋トレではなく、体の「使い方」を再教育するメソッドです。
私たちは無意識のうちに、利き手や利き足に頼った動作を繰り返しています。
たとえばカバンをいつも同じ側で持つ、立つときに片脚に体重をかける、スマホを片手で操作する──。
こうした日常動作が積み重なることで、筋肉や関節に偏りが生まれます。
ピラティスは、骨・筋肉・呼吸を整え、体の中心からバランスを取り戻すための最適な方法です。
この記事では、「身体の左右差」がなぜ起こるのか、放置するとどんな影響が出るのか、そしてピラティスがどのように根本改善に導くのかを解説します。
筋力だけでなく、神経や感覚、呼吸までも整えるピラティスの力を、ぜひ知ってください。

左右差の正体:筋力・柔軟性・骨格・神経のアンバランス
私たちの身体は、常にわずかな「非対称性」を持っています。
心臓は左に、肝臓は右に位置し、内臓の配置そのものが完全な左右対称ではありません。
しかし、それに加えて筋肉の使い方や姿勢のクセによって、本来必要なバランスを超えた「偏り」が生まれてしまいます。
この左右差は、筋力のアンバランス(片側ばかり使う)、柔軟性の違い(片方が硬い)、骨格の歪み(骨盤や脊柱のねじれ)、神経の伝達の差(動きの感覚が鈍い側)といった複数の要因が絡み合って生じます。
たとえば右利きの人は、右手で物を取る、右足で踏み出す、右側に体重を預ける──といった動作を無意識に繰り返しています。
このように「片側優位な動き」が続くと、片方の筋肉が過剰に緊張し、反対側が弱化します。
結果として骨盤や背骨の軸がずれ、全身のバランスが崩れてしまうのです。
また、神経の働きも見逃せません。
脳は左右で異なる役割を担っており、動作や感覚にも微妙な違いを作り出します。
ピラティスでは、脳と身体の「つながり(ニューロマッスルコントロール)」を整えるために、意識的に両側を均等に使う動きを学びます。
これにより、単に筋肉を鍛えるのではなく、“神経レベル”での左右差改善が可能になります。
左右差があると何が起こるか:肩こり・腰痛・膝の痛み・姿勢の歪み
身体の左右差は、見た目だけでなく、機能的な不調の原因にもなります。
たとえば、肩の高さが違うと首や肩まわりの筋肉に余計な緊張が入り、慢性的な肩こりや頭痛を引き起こします。
また、骨盤の高さやねじれが生じると、腰や股関節にかかる負担が増し、腰痛や膝の痛みに発展するケースも多いです。
特に骨盤の傾きによる「脚長差(片足が長く見える)」は、身体のバランスを大きく崩し、歩行や立位の安定性に影響を与えます。
さらに厄介なのは、左右差によって「片側ばかりが疲れる」「姿勢が崩れやすい」などの習慣的なパターンが脳に記憶されることです。
つまり、無意識のうちに“偏った姿勢”が「普通」として定着してしまうのです。
これが続くと、どんなにマッサージやストレッチをしても、根本的な改善が難しくなります。
ピラティスが注目されている理由は、この「無意識のクセ」にアプローチできる点にあります。
呼吸と動作を組み合わせながら、身体の中心(コア)を安定させることで、偏った筋肉の使い方をリセットし、左右のバランスを再教育していきます。
身体の“正しい位置”を感じながら動くトレーニングは、痛みを防ぐだけでなく、再発を防ぐ基盤にもなります。
見逃されがちな左右差:成長期からのクセ・利き手・日常動作の影響
左右差の原因は、実は子どものころから始まっています。
たとえば、学生時代の部活動で特定の動作を繰り返した、片側でカバンを持って通学した、机に向かう姿勢が偏っていた──。
これらの習慣が蓄積され、大人になってからの姿勢や体の使い方に影響を及ぼしています。
社会人になると、さらに長時間のデスクワークやスマホ操作が加わります。
パソコンのマウスを常に右手で使う、同じ方向に体をひねる姿勢で座るなど、偏った動作が日常化し、左右差が固定されていきます。
そして、「自分ではまっすぐ立っている」と思っても、鏡で見ると肩や骨盤がずれている、ということがよくあります。
ピラティスは、こうした無自覚の左右差を「感じる」ことから始まります。
動きの中で、どちらの足が安定しているか、どちらの肩が上がりやすいかなどを丁寧に観察しながら、自分の体と向き合う。
その“気づき”が、修正の第一歩になるのです。
なぜピラティスが左右差改善に選ばれているのか

筋トレ・ストレッチとの違い:“使い方”を整えるメソッド
一般的な筋トレは、筋肉の強化を目的としています。
ストレッチは柔軟性を高めることが主な目的です。
しかし、ピラティスは「筋肉をどう使うか」という“コントロール”を重視します。
つまり、筋肉を単に鍛えるのではなく、正しい順序・バランス・タイミングで動かす練習を行うのです。
この点が、左右差の改善において非常に重要です。
筋力の差や柔軟性の差があっても、使い方を変えることでバランスは整っていきます。
ピラティスでは、左右の動きを比較しながら「弱い方を意識して使う」「強い方を休ませる」といった調整を自然に行えます。
こうした繊細なアプローチが、体を対称に近づけるカギになります。
呼吸・体幹・アライメントを同時に整えるピラティスの強み
ピラティスではすべての動作に呼吸を伴います。
この呼吸が、左右差改善の土台になります。
胸郭を左右均等に広げる意識を持つことで、肋骨や背骨の動きが滑らかになり、体幹の深層筋(腹横筋、多裂筋、骨盤底筋など)がバランスよく働きます。
また、ピラティスは「ニュートラルポジション」という概念を大切にしています。
これは、骨盤と背骨が理想的な位置関係を保った状態のこと。
左右どちらにも傾かず、体の中心(センターライン)を軸に動く練習を繰り返すことで、日常の姿勢や歩行も自然に安定していきます。
たとえば、マットピラティスで行う「シングルレッグストレッチ」や「スパインツイスト」などは、片側ずつ動かすエクササイズです。
左右の感覚の違いを意識しながら行うことで、バランスの取れた神経伝達が促され、体の軸が整っていきます。
呼吸・体幹・姿勢を一体化させるピラティスだからこそ、筋力だけでは解決できない“感覚のズレ”にまで働きかけられるのです。
日常の動き・クセをリセットして、左右差を根本から変えていく流れ
ピラティスの最大の特徴は、レッスンで得た感覚が「日常生活に活かせる」ことです。
エクササイズ中に身につけた体の使い方や重心感覚は、歩く・座る・立つといった日常動作の中で自然と再現されます。
これにより、無意識の偏りが徐々にリセットされていきます。
たとえば、「片足に重心をかけすぎない」「左右均等に体を伸ばす」「デスクワーク中に呼吸を止めない」。
これらはどれも、ピラティスを通して身につく“左右差を作らない習慣”です。
根本的な改善とは、こうした「日常の中でどう動くか」の積み重ねによって生まれます。
ピラティスを継続することで、身体のバランスが整うだけでなく、疲れにくく快適に過ごせる体へと変わっていくのです。
自分の身体の左右差に気づくためのセルフチェック&基本エクササイズ

鏡・写真・動画で見る左右差チェックポイント:肩・骨盤・脚長差
まずは、自分の体を「見ること」から始めましょう。
ピラティスの第一歩は、“気づくこと”です。
鏡の前にまっすぐ立ち、肩の高さ、骨盤の傾き、膝の向き、足裏の重心を確認します。
写真や動画を撮ってみると、肉眼では気づかない微妙な差も見えてきます。
特に次のポイントを意識して観察してみましょう。
・左右の肩の高さは同じか
・骨盤の高さやねじれがないか
・両膝がまっすぐ前を向いているか
・立ったとき、どちらかの足に体重を乗せていないか
こうして客観的に自分の姿勢を見ることで、体の偏りに“気づく感覚”が育ちます。
この「自覚」が、改善の出発点です。
左右差に働きかける代表的なピラティス動作
次に、日常で簡単に行えるピラティスの基本動作をご紹介します。
どれもマット一枚あればできるものばかりです。
① シングルレッグストレッチ
仰向けで片膝を胸に引き寄せ、もう一方の脚を伸ばします。
呼吸を止めず、左右を交互に繰り返します。
左右の脚を動かす際、腹筋の使い方や骨盤の動きに違いを感じてみましょう。
“弱い側”に気づくことがバランスを取り戻す第一歩です。
② サイドキック
横向きになり、上側の脚をゆっくり前後に動かします。
骨盤が後ろに倒れないようにコントロールするのがポイント。
左右差を感じながら、骨盤と体幹の安定を意識しましょう。
③ スパインツイスト
背筋を伸ばして座り、上半身を左右にひねります。
どちら側にひねりやすいか、動きのスムーズさに差がないかを確認します。
呼吸と共に背骨をしなやかに動かすことで、ねじれの偏りを整えます。
これらの動作は、体の“左右を比較しながら動く”ことが大切です。
意識して練習することで、脳と筋肉の連携(神経‐筋コントロール)が高まり、動きの精度が上がります。
日常で使える“左右差を自覚する”習慣
ピラティスの効果を最大化するには、日常の中で「意識する時間」を増やすことが大切です。
以下のような小さな意識改革が、実は最も効果的です。
・立つときは、両足に均等に体重を乗せる
・荷物を持つ手を日ごとに変える
・スマホを見る位置を中央にする
・座るときは、坐骨が左右均等に当たるよう意識する
このような習慣を積み重ねることで、「無意識の左右差」を徐々にリセットできます。
ピラティスの目的は、レッスンの時間だけ整えることではなく、“日常の中で正しく動ける身体”をつくることにあります。
左右差を改善すると、こんな変化が生まれる

疲れにくく・動きやすくなる身体に変わる
左右差が整うと、まず「疲れにくくなる」という変化が現れます。
左右どちらかに過剰な負担がかかっていた身体が、均等にエネルギーを使えるようになるためです。
立っていても、歩いていても、体の軽さを実感できるようになります。
呼吸も深くなり、代謝が上がることで日常のパフォーマンスも向上します。
見た目の左右バランスが整って自信が上がる
身体のバランスが整うと、見た目の印象も変わります。
片肩が下がる、顔が傾く、骨盤が歪むといった非対称のクセが減り、姿勢全体が整っていきます。
鏡に映る自分が“まっすぐ立っている”感覚を得られることは、大きな自信につながります。
無理に姿勢を作るのではなく、「自然体で美しくいられる」ことが、ピラティスの本質的な魅力です。
運動パフォーマンスも日常の動きもラクになる
ピラティスはアスリートのパフォーマンス向上にも用いられています。
それは、左右のバランスが取れた身体が“動作の効率”を高めるからです。
たとえば、ランニングやゴルフ、ヨガなどでも、左右差が整うことでフォームの安定性が増します。
日常でも、階段を上る・荷物を持ち上げるといった動作がスムーズに。
「使いやすい身体」へと変わることで、動くことそのものが楽しくなっていきます。
“自分の身体を感じて使える”習慣が、長く健康でいられる鍵に
左右差が整うと、単に体が軽くなるだけでなく、「自分の身体をどう使っているか」に敏感になります。
これは、年齢を重ねても健康を維持するうえで非常に重要なポイントです。
ピラティスを続けることで、関節や筋肉を守る“動き方”が身につき、ケガの予防にもつながります。
つまり、左右差改善は「未来の身体を守る投資」なのです。
不調を“敵”ではなく“メッセージ”として受け止められるようになると、心の余裕も生まれます。
ピラティスは、単なる運動ではなく“自分と向き合う時間”なのです。
解剖学的な観点で見る、ピラティスが身体の左右差や不調改善に有効な理由

腹横筋・骨盤底筋・多裂筋:左右差を支える深層筋の役割
ピラティスでは、身体の“コア”と呼ばれる深層筋を鍛えます。
この中でも、腹横筋・骨盤底筋・多裂筋は左右差の改善に直結する重要な筋肉です。
これらがバランスよく働くことで、骨盤や背骨が中心で安定し、偏りのない動きをサポートします。
肩甲骨・骨盤・股関節の連動性が左右バランスに与える影響
人の動きは、上半身と下半身の連動で成り立っています。
たとえば、右腕を振るときには左脚が支えるなど、常に交差する動きが起きています。
この「クロスパターン」が崩れると、肩や骨盤の位置が不安定になり、左右差が悪化します。
ピラティスは、こうした“体幹の連動”を再教育するエクササイズです。
動きの中で左右の筋肉が協調する感覚を育て、歪みの根本を整えていきます。
筋膜・神経・感覚統合:左右差が慢性化するプロセスと改善のポイント
筋膜は全身を包む“ボディスーツ”のような存在です。
一部が固まると、離れた部位にも影響が及びます。
ピラティスでは、滑らかな動きと深い呼吸によって筋膜の張力を整え、身体全体の統合を促します。
さらに、神経系にもアプローチし、脳と身体の「左右の感覚マップ」を再構築します。
これにより、無意識の偏りが修正され、動きの再現性が高まります。
痛みの軽減につながるのです。
呼吸筋・肋骨・胸郭:左右差を整えるための“動く基盤”
左右差の改善で忘れてはならないのが“呼吸”です。
呼吸筋(横隔膜・肋間筋など)が硬くなると、胸郭の動きが偏り、姿勢にも影響します。
ピラティスの呼吸法は、肋骨を左右均等に広げ、胸郭を立体的に動かすことを目的としています。
これにより、体幹の内圧が安定し、左右の筋肉がバランスよく働くようになります。
左右差は、誰にでもある“自然な個性”ですが、その差が大きくなりすぎると、体の不調や姿勢の崩れに直結します。
ピラティスは、筋肉・骨格・呼吸・神経といった全ての要素に働きかけ、左右差を「感じ、整える」ための最適なメソッドです。
エクササイズの積み重ねによって、体だけでなく心までバランスが整っていくのを感じられるでしょう。
大切なのは、“完璧な左右対称”を目指すことではなく、「自分の体を理解して心地よく使うこと」。
小さな気づきを重ねることで、動くことがもっと楽しく、もっと自由になります。
そして、その変化こそが、ピラティスがもたらす本当の「整う感覚」です。
身体が整えば、心も軽く、毎日がもっと快適に変わっていくはず。
今日から、あなたも自分の体と向き合う時間をつくってみませんか?
【2025年1月4日!大森・大森駅チカに「パーソナルピラティススタジオ」新規オープン!】

大森、大森駅エリアの皆さま、お待たせしました!
「パーソナルピラティス専門スタジオ」 がついに 1月4日にグランドオープンいたしました!
大森駅から徒歩圏内という好アクセスで、忙しい日常の中でも通いやすく
理想の体を手に入れるお手伝いをいたします♪
【オープン記念!初回体験キャンペーン実施中】
〜あなたもピラティスで変化を感じてみませんか?〜
グランドオープンを記念しまして
現在、 特別価格にて「パーソナルピラティス体験レッスン」をご提供中です!
- 場所:東京都大田区大森北1丁目33−4 湯建大森北ビル Ⅱ 2F
- 内容:マンツーマンのパーソナルピラティス体験レッスン
- 対象:ピラティス初心者から経験者まで、どなたでも大歓迎!
この機会に 「大森、大森駅エリア」 で質の高いパーソナルピラティスを利用して
心も体もリフレッシュしながら理想の体づくりを始めてみませんか?
【大森・大森駅のパーソナルピラティスが選ばれる理由】
大森駅近の好立地:駅から徒歩圏内で通いやすいスタジオ。
完全個別のマンツーマン指導:一人一人の体に合わせたパーソナルピラティスで理想の結果へ導きます。
姿勢改善・体幹強化・ダイエット:お客様の目標に合わせたプログラムをカスタマイズ。
初心者でも安心:経験豊富なインストラクターが丁寧にサポートします。
大森、大森駅近くでパーソナルピラティスを体験したい方に最適な環境が整っていますよ。
【こんな方におすすめです!】
①美しく健康的な体づくりをしたい方
②大森・大森駅近くで通いやすい「パーソナルピラティス」スタジオをお探しの方
③姿勢改善や体幹を強化したい方
④運動が苦手な初心者の方でも安心して始められます!
- 冷え性に悩む女性へ〜ピラティスで内側から整える方法〜
- 前屈できないのは硬いから?ピラティスで変わる身体の使い方
- ピラティスがダンサーやモデル・アーティストに人気な理由
- 運動習慣を身につけたい人にピラティスがおすすめな理由
- 年明けに始めたい!年末年始太りを防ぐパーソナルピラティスの効果
関連記事
-
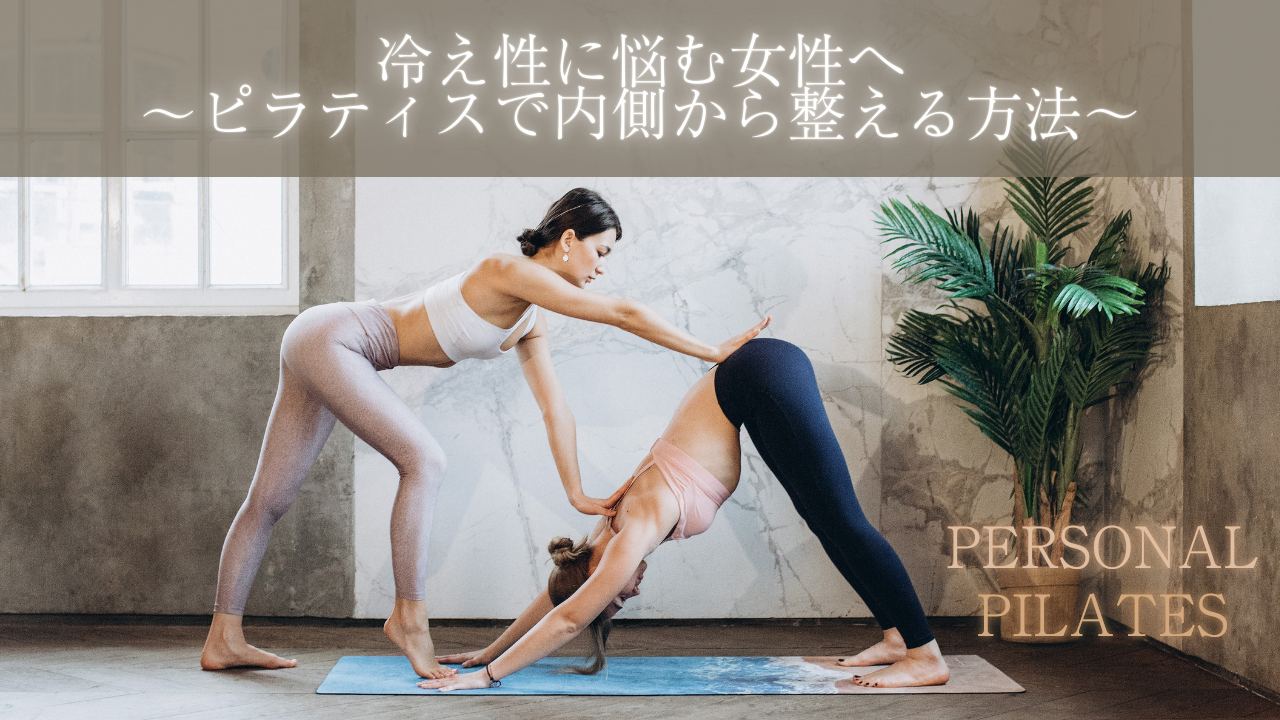
冷え性に悩む女性へ〜ピラティスで内側から整える方法〜
ピラティス体幹冷え性 -
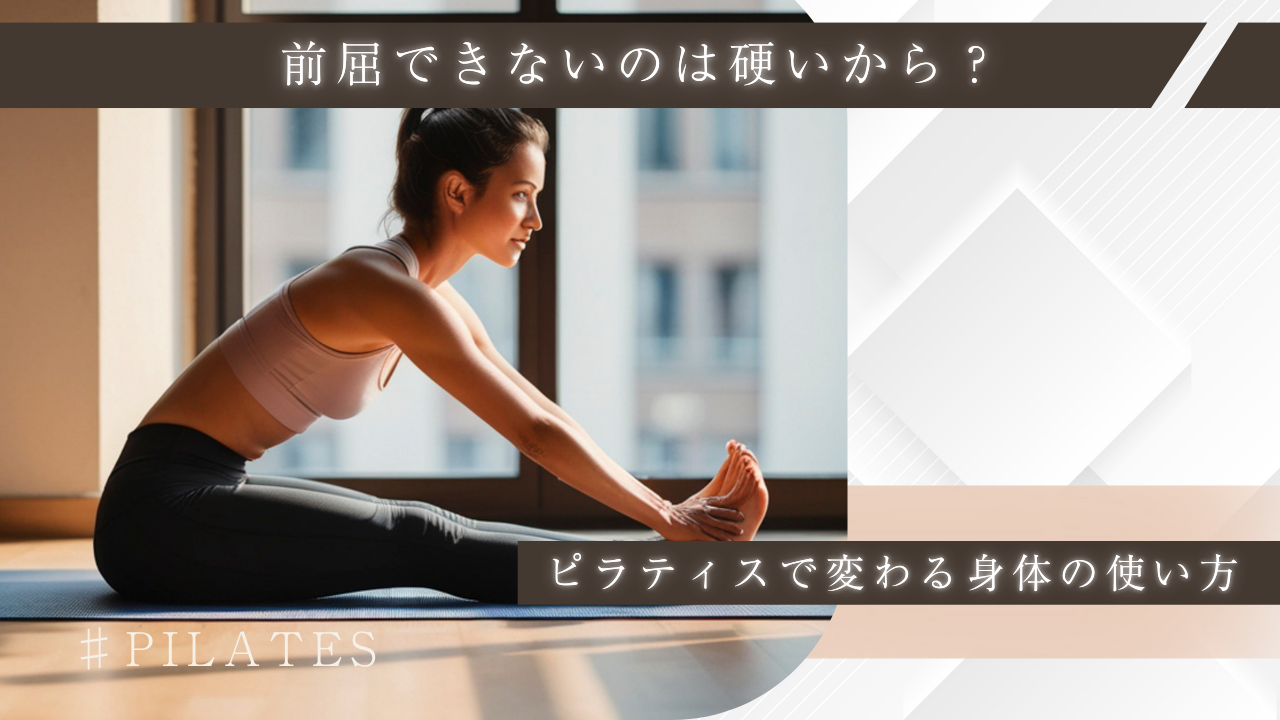
前屈できないのは硬いから?ピラティスで変わる身体の使い方
ピラティス体幹姿勢改善柔軟性UP -
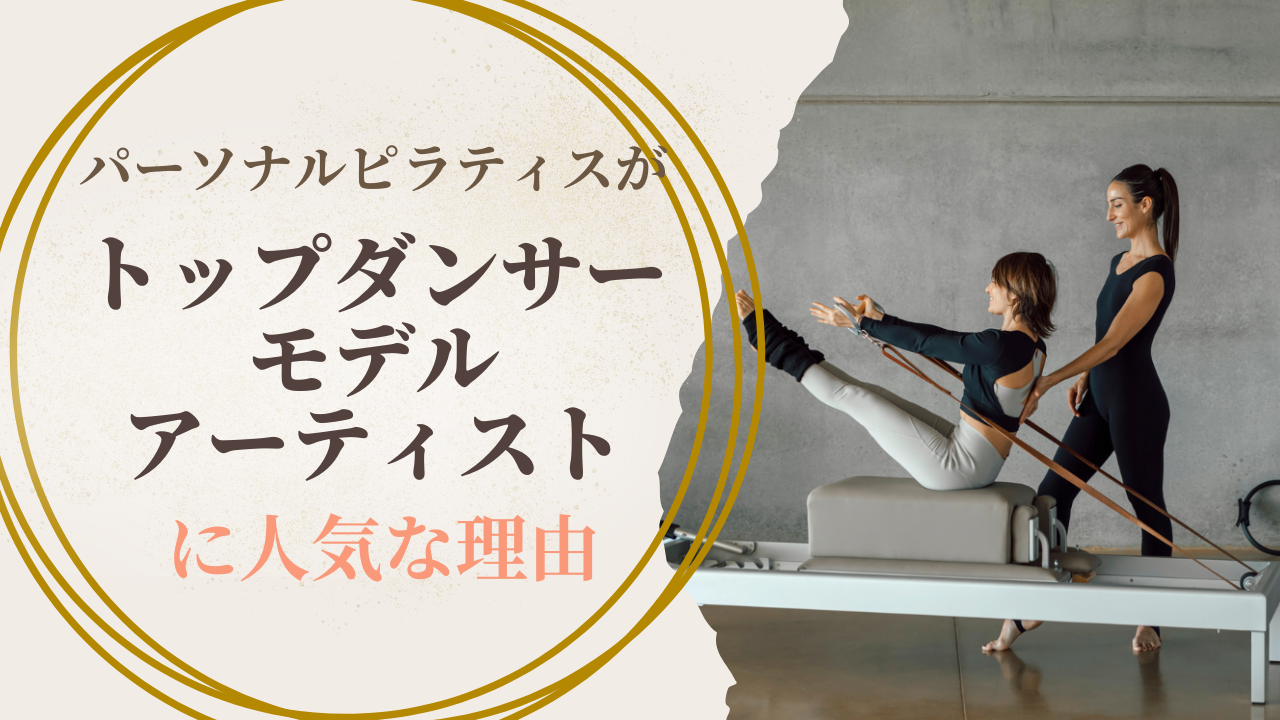
ピラティスがダンサーやモデル・アーティストに人気な理由
ピラティス体幹姿勢改善柔軟性UP -

運動習慣を身につけたい人にピラティスがおすすめな理由
ピラティス体幹姿勢改善柔軟性UP -

年明けに始めたい!年末年始太りを防ぐパーソナルピラティスの効果
ピラティス体幹姿勢改善柔軟性UP -

ゴルフの上達は体幹から?ピラティスで学ぶ正しい身体操作
ピラティス体幹姿勢改善柔軟性UP -

ピラティス初心者が感じやすい変化ベスト3
ピラティス体幹姿勢改善柔軟性UP -
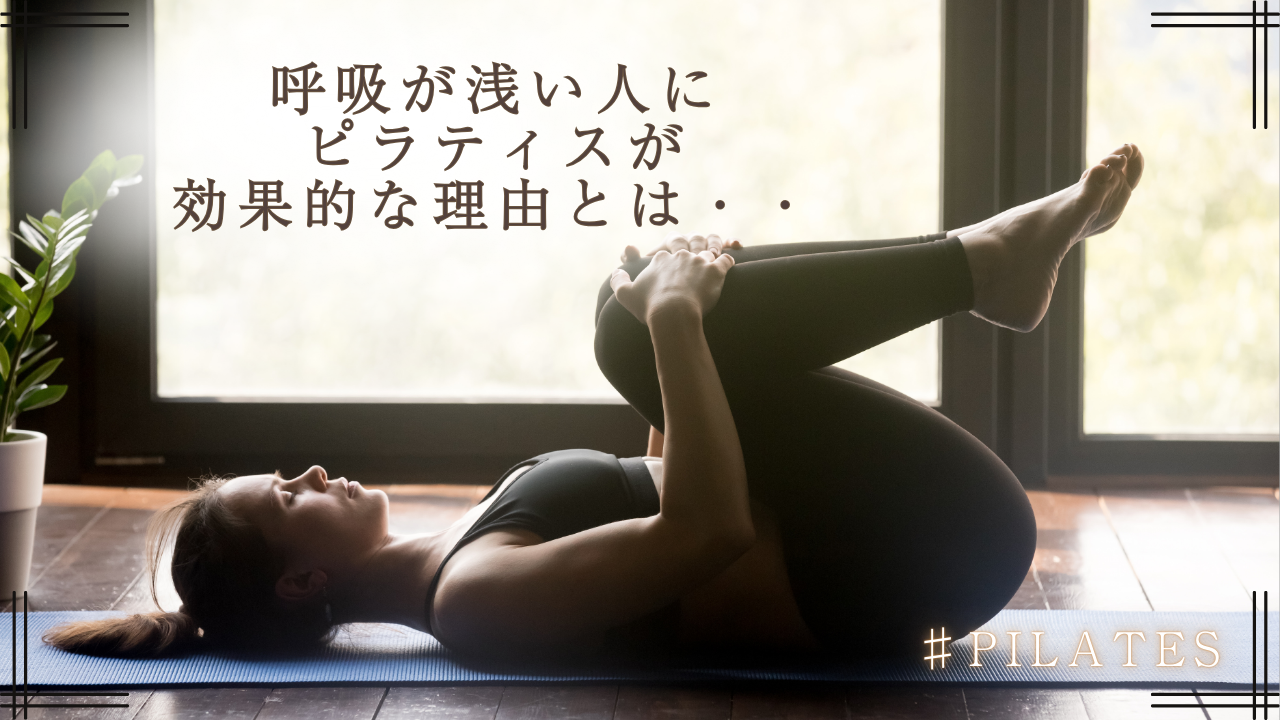
呼吸が浅い人にピラティスが効果的な理由
ピラティス体幹姿勢改善柔軟性UP -

ピラティスで叶える“くびれ”メイク術
ピラティス体幹姿勢改善 -

姿勢が整うと仕事がはかどる!ピラティスがデスクワーク疲労に効果的なワケ
ピラティス体幹姿勢改善 -

身体のラインが変わる!美姿勢を作るピラティスの原則
ピラティス体幹姿勢改善 -

立っているだけで疲れる原因って?ピラティスで改善できるワケ
ピラティス体幹姿勢改善